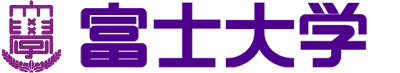第3回 地域活性化論 「地域活性化とSDGs/ESD」が関上哲教授により行われました。
授業関係
9月28日の第3回は関上哲教授による「地域活性化とSDGs/ESD」が行われました。基本的なSDGsへの接近を地域活性化論と絡めると人材育成(ESD)に必然に繋がるとした特色のある講義でした。
受講学生には事前課題があり、その予習レスポンスカードには地域活性化に対する学生の問題意識の違いが示され、課題ではSDGsの17目標ならびに169インデックスにどのように関連づけられているかが考察されていました。
講義内容は、岡田学長の地域の定義に触れながら、なぜ地域を問題にするのか、地域の構成と図式化が示されたのち、特に講義では「地域」を「ローカルな知」として「時間的・空間的に限定された一時的なもの」と見ている点が、地域活性化を考える際に重要であるとし、その特質の特徴が示されました。
その後、今日の地域はグローバライゼーションの影響を受けて疲弊しており、そのためアンチグローバライゼーションこそが地域には必要と指摘し、内発的な開発こそが求められていることを強調されました。
実践的な事例として、花巻市の大迫町での街並み整備に取組む関上ゼミ生の活動とその具体的成果の紹介がありました。ESDを中心とする地域でのSDGs活動に対して、今後とも大きな期待が寄せられている、という講義内容でした。
写真1
左から: 関上哲教授(講師) 遠藤元治教授、吉田哲朗教授

写真2 授業風景

写真3 授業風景

受講学生には事前課題があり、その予習レスポンスカードには地域活性化に対する学生の問題意識の違いが示され、課題ではSDGsの17目標ならびに169インデックスにどのように関連づけられているかが考察されていました。
講義内容は、岡田学長の地域の定義に触れながら、なぜ地域を問題にするのか、地域の構成と図式化が示されたのち、特に講義では「地域」を「ローカルな知」として「時間的・空間的に限定された一時的なもの」と見ている点が、地域活性化を考える際に重要であるとし、その特質の特徴が示されました。
その後、今日の地域はグローバライゼーションの影響を受けて疲弊しており、そのためアンチグローバライゼーションこそが地域には必要と指摘し、内発的な開発こそが求められていることを強調されました。
実践的な事例として、花巻市の大迫町での街並み整備に取組む関上ゼミ生の活動とその具体的成果の紹介がありました。ESDを中心とする地域でのSDGs活動に対して、今後とも大きな期待が寄せられている、という講義内容でした。
写真1
左から: 関上哲教授(講師) 遠藤元治教授、吉田哲朗教授

写真2 授業風景

写真3 授業風景