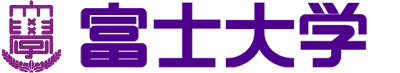学生が見た“食”の現場 小麦から学ぶ農業のリアル
授業関係
広がる麦畑で考えた、私たちの「食」のこれから— 海邉ゼミの3年生、小麦の収穫に挑む —
初夏の花巻・太田地区。目の前に広がる金色の麦畑で、大学生たちが真剣な表情でコンバインに乗り込み、小麦の収穫に汗を流していました。いま、富士大学・海邉健二ゼミが取り組むフィールドワークが注目されています。
「食」を学ぶということは、土とふれ合うことから始まる
この活動は、地域の産業を実際に肌で感じながら学ぶゼミの取り組みの一環です。これまでも玉ねぎの収穫や田植え・稲刈りなど、農業のリアルに触れてきたゼミ生たち。今回は、収穫の最盛期を迎えた小麦にフォーカスし、事前学習から現地体験までを一貫して行いました。
小麦の自給率が約15%という現実や、播種から収穫、製粉、そしてパンやパスタへと姿を変えるまでの流れ。知識を得たうえで、農事組合法人の方から現場の声や収支の話を直接聞けたことで、教科書では得られないリアルな気づきがありました。
麦の穂の向こうに見えた、当たり前じゃない日常
学生のひとりはこう語ります。「広がる麦畑の景色に圧倒されました。普段の食卓に並ぶ食材の背景には、こんなに多くの努力があることに気づき、もっと食を大切にしたいと思いました」。
スーパーに並ぶ小麦粉を見ることはあっても、その原料である「小麦の粒」を見たことがなかったという学生も少なくありません。フィールドワークのなかで、稲との違いや栽培の工夫に驚きながら、学びを深めました。
「小麦って、どこでどう作られているんだろう?」そんな素朴な疑問が、学びの入口になるのかもしれません。
このフィールドワークの様子は、7月4日付の岩手日日新聞(12面)にも掲載されました。(画像掲載許諾済み)
これからも富士大学では、地域と共に「生きた学び」を続けていきます。あなたなら、どんな現場で何を感じてみたいですか?


初夏の花巻・太田地区。目の前に広がる金色の麦畑で、大学生たちが真剣な表情でコンバインに乗り込み、小麦の収穫に汗を流していました。いま、富士大学・海邉健二ゼミが取り組むフィールドワークが注目されています。
「食」を学ぶということは、土とふれ合うことから始まる
この活動は、地域の産業を実際に肌で感じながら学ぶゼミの取り組みの一環です。これまでも玉ねぎの収穫や田植え・稲刈りなど、農業のリアルに触れてきたゼミ生たち。今回は、収穫の最盛期を迎えた小麦にフォーカスし、事前学習から現地体験までを一貫して行いました。
小麦の自給率が約15%という現実や、播種から収穫、製粉、そしてパンやパスタへと姿を変えるまでの流れ。知識を得たうえで、農事組合法人の方から現場の声や収支の話を直接聞けたことで、教科書では得られないリアルな気づきがありました。
麦の穂の向こうに見えた、当たり前じゃない日常
学生のひとりはこう語ります。「広がる麦畑の景色に圧倒されました。普段の食卓に並ぶ食材の背景には、こんなに多くの努力があることに気づき、もっと食を大切にしたいと思いました」。
スーパーに並ぶ小麦粉を見ることはあっても、その原料である「小麦の粒」を見たことがなかったという学生も少なくありません。フィールドワークのなかで、稲との違いや栽培の工夫に驚きながら、学びを深めました。
「小麦って、どこでどう作られているんだろう?」そんな素朴な疑問が、学びの入口になるのかもしれません。
このフィールドワークの様子は、7月4日付の岩手日日新聞(12面)にも掲載されました。(画像掲載許諾済み)
これからも富士大学では、地域と共に「生きた学び」を続けていきます。あなたなら、どんな現場で何を感じてみたいですか?