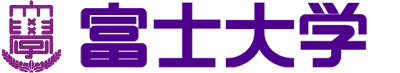| 文字サイズ |
|---|
※翻訳が不十分な場合もございます。
ご了承下さい。
ご了承下さい。
トップ > 地域の皆さまへ > 公開授業 > 公開授業「地域創生論」
富士大学公開授業「地域創生論」
申込先:富士大学 総務部 TEL 0198-23-6221
電話でお申込みください。
受講料:1回につき300円(受付時にいただきます。)
資料のみ希望の方には郵送いたします。(郵送料120円)
希望の方は、富士大学 総務部 までお問い合わせください。
[富士大学 総務部 TEL 0198-23-6221]
電話でお申込みください。
受講料:1回につき300円(受付時にいただきます。)
資料のみ希望の方には郵送いたします。(郵送料120円)
希望の方は、富士大学 総務部 までお問い合わせください。
[富士大学 総務部 TEL 0198-23-6221]
地域の現状と地域創生の取組を理解することを目標とし、開講の主旨から、多くの外部講師の協力を得て授業を展開します。 ================ 「地域創生論」は、公開授業として、地域そして学生の多くの皆さんに定着し、好評をいただいております。 今年度も様々な分野で活躍をされている方々を講師としてお招きしました。 「政策」「生活」「復興」「支援」「希望」「医療」「環境」「地産地消」ほか地域社会の「現在」をお話しいただきます。 各回のキーワードを読み解き、「地域創生」について意見を交わしましょう。 |
概要
| 実施日時 | 2024年4月11日~7月18日(全て木曜日) 14時10分~15時40分(4時限目) |
|---|---|
| 会場 | 富士大学 5号館1階 階段教室 |
| 実施講義回数 | 全15回 15回目はシンポジウムを行う。 |
| 対象学年 | 本学学生2~4年生 |
日程および講義内容
諸般の事情により内容が変更になる場合があります。
1.4/11
地域創生(論)の意義と地域創生論のいろいろ
富士大学長 岡田 秀二
2.4/18
都市と地方をかきまぜる
(株)雨風太陽代表取締役 高橋 博之 氏
3.4/25
地域農業の新しい可能性
(株)耕野代表取締役 安藤 誠二 氏
4.5/2
地域主導でのエネルギー事業作り
紫波グリーンエネルギー(株) 代表取締役 山口 勝洋 氏
5.5/9
グローバルで戦う地域の先進企業の哲学
(株)アイオー精密代表取締役社長 鬼柳 一宏 氏
6.5/16
地域づくりとサステナビリティ
朝日新聞社 SDGs ACTION! 創刊編集長 高橋 万見子 氏
7.5/23
夢しか実現するものはない
葛巻町長 鈴木 重男 氏
8.5/30
いわて県民計画(第2期アクションプラン)について
ー人口減少対策などを中心として―
岩手県政策企画部 西野 文香氏
9.6/6
SDGs が果たす役割と持続可能な地域の未来
岩手県中小企業家同友会事務局長 菊田 哲 氏
10.6/13
スポーツ×人間力=無限大
NPO法人フォルダ理事長
長屋 あゆみ 氏
11.6/20
南部美人の挑戦 ~岩手から世界へ!~
(株)南部美人代表取締役社長 久慈 浩介 氏
12.6/27
地域資源・エネルギーが地域の新軌道を拓く
軽米町長 山本 賢一 氏
13.7/4
花巻市の現状と課題
花巻市長 上田 東一 氏
14.7/11
~知ることから始めよう
食・環境を守るための消費者運動~
岩手県生活協同組合連合会専務理事 吉田 敏恵 氏
15.7/18
【シンポジウム】
地域創生の実現に向けてⅧ
富士大学長 岡田 秀二
岩手県政策企画部 小野 博氏
(株)岩手日報社 編集局報道部
地域創生(論)の意義と地域創生論のいろいろ
富士大学長 岡田 秀二
2.4/18
都市と地方をかきまぜる
(株)雨風太陽代表取締役 高橋 博之 氏
3.4/25
地域農業の新しい可能性
(株)耕野代表取締役 安藤 誠二 氏
4.5/2
地域主導でのエネルギー事業作り
紫波グリーンエネルギー(株) 代表取締役 山口 勝洋 氏
5.5/9
グローバルで戦う地域の先進企業の哲学
(株)アイオー精密代表取締役社長 鬼柳 一宏 氏
6.5/16
地域づくりとサステナビリティ
朝日新聞社 SDGs ACTION! 創刊編集長 高橋 万見子 氏
7.5/23
夢しか実現するものはない
葛巻町長 鈴木 重男 氏
8.5/30
いわて県民計画(第2期アクションプラン)について
ー人口減少対策などを中心として―
岩手県政策企画部 西野 文香氏
9.6/6
SDGs が果たす役割と持続可能な地域の未来
岩手県中小企業家同友会事務局長 菊田 哲 氏
10.6/13
スポーツ×人間力=無限大
NPO法人フォルダ理事長
長屋 あゆみ 氏
11.6/20
南部美人の挑戦 ~岩手から世界へ!~
(株)南部美人代表取締役社長 久慈 浩介 氏
12.6/27
地域資源・エネルギーが地域の新軌道を拓く
軽米町長 山本 賢一 氏
13.7/4
花巻市の現状と課題
花巻市長 上田 東一 氏
14.7/11
~知ることから始めよう
食・環境を守るための消費者運動~
岩手県生活協同組合連合会専務理事 吉田 敏恵 氏
15.7/18
【シンポジウム】
地域創生の実現に向けてⅧ
富士大学長 岡田 秀二
岩手県政策企画部 小野 博氏
(株)岩手日報社 編集局報道部
狙い: 地域創生政策が2巡目を展開中である。しかし、地方の持続性にはなお課題が多い。生活条件格差はむしろ拡大傾向にある。コロナ禍を経て一層の苦境に立たされてもいる。だからこそ、と言えようが、日本に限らず世界中で市場論理万能のシステムを抑え、人間らしさを尊重する仕組みや多様な価値観からなる調整・バランス型の経済社会構造が提案され実施に移されるようになってきた。しかし、グローバル化の大きなうねりにブレーキを踏みつつ、地域持続型の経済社会形成へシフトチェンジするのは至難のことである。地域の実情に応じつつ、関連する多くのセクターの協力が必要であるので、各回の報告から多くを学び、一人一人がひとりが参加意識を高めてもらいたい。 到達目標: 地域の実態を理解するとともに、地域課題は何か、課題解決のための政策はどういうものかを理解し、説明できる。 講義方法等: 本学学生を対象とした講義を、地域や県内の関心を持つ多くの人にも開放し、公開のものとする。 授業90分中、実質講義時間は60分とし、質疑による理解の醸成を図る時間を30分とることとする。 |